久しぶりの本紹介です。
庭・日本美の創造 吉村貞司著 六興出版 昭和56年初版発行
著者略歴:1908年 福岡県生まれ
1931年 早稲田大学独文科卒業
現在(発行当時です)杉野女子大学教授
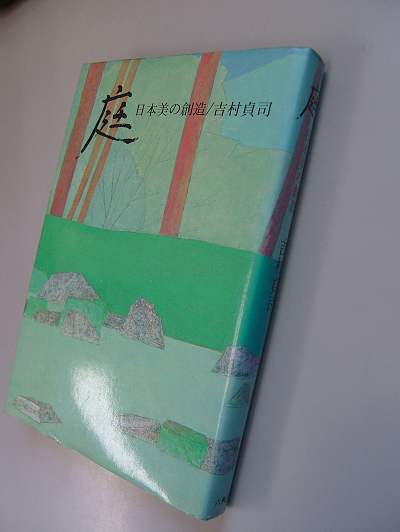
代表的な日本の名庭園についての随筆集です。
技法的な面からだけではなく、作庭の時代背景、作者の精神性などから芸術としての庭園の美を読み解こうという本だと思います。
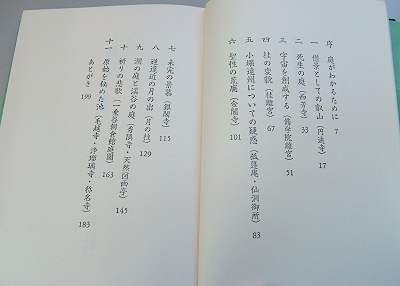
古書店で十数年前に入手後、ここしばらく目を通す機会がありませんでしたが、先日の京都への研修時に
円通寺に立ち寄ったことから、久しぶりに読んでみました。
これがなかなか深くて印象的でした。
借景の部分が興味深いので円通寺の所の内容を一部紹介しますと・・・
「数多い京の庭で、すきな名を上げよと乞われたら、私はいつしか円通寺をあげるようになってしまった。
(中略)
住持は平庭のむこう側のいけがきの高さについて話してくれたことがあった。おとなが立って、肩まで位かと思っていたところが、そばによっていっぱいに腕をのばしてもとどかないという。三メートル前後もあるという。私には意外だった。
同時に庭のひろさが百六十坪ほどと言われ、意外に広い面積にただ、ほうと感じるに終わっていたのが、どうして広い庭を狭く見せているだろうかと心にひっかかった。
(中略)
私は何年もこの問題をとくことができなかった。
(中略:西本願寺書院の鴻の間における逆遠近を使った空間の密度についての考察)
私は庭をせまく見せ、小さく見せようとした意味が急にわかり出した。
庭の空間を緻密にする。その濃密さが比叡山をゆったり大きく見せる。
考えてみると理論は単純だった。つまり、庭が狭く見えるほど、山は大きく見える。庭が広いと山はそえものになってしまう。
これは誰にでも理解できる単純な原理だ。
(中略)
天寿山資福禅寺
彼(後水尾上皇のこと)は幡枝を寺にしたときの寺号まで考えていた。<天寿><資福>に彼の願いが込められていたのだ。幕府はそれを意地悪くゆるさず、文英尼による円通寺となった。<円通寺>---なんと女性的なやわらかな感覚のやさしさであることよ。」

(2009.1の円通寺:この庭がそんなつくりになっていたとは!)

(円通寺のしおり:紅葉の円通寺もすばらしいですね)
この本はアマゾン等で古書が入手可能のようです。
円通寺。
京都に行くことがあれば日程に加えてみてはいかがでしょう。



